現在使用されている『避雷針』の難点
|
超容量衝撃電圧発生装置を用いて実験を行った結果によると「避雷針」では、電撃距離が長くなると先端での放電(上向ストリーマ)が一定とはならず、側面を含む多数の点からも出発してしまい、その結果として当然先端先で落雷を受け止めるべき物が側面でも落雷を受けているのが確認された報告がされている。(図ー1)そのことから落雷をすべて吸収できず雷は行き先を失ってどこへ落下するか見当もつかず、人身事故域は、火災を含めた物損事故へと発展することも予想されます。また側面で受けた落雷を全て吸収できず落雷の瞬間想像もつかぬ「大電磁波」が発生し、従来アンテナ・無線・太陽光発電・その他の設備などを保護する目的で設置したものが、逆に一番危険な状態になることが予想されます。あるテレビ放映の中で某教授は「電磁波は1キロ先までも飛ぶことがある」と言っておられました。また欧米などでは、その「避雷針」があったための被害として訴訟にまで発展するといわれ、遠からず、日本国内でもそのような責任問題になるのではないかと予測されます。(図ー2)
|
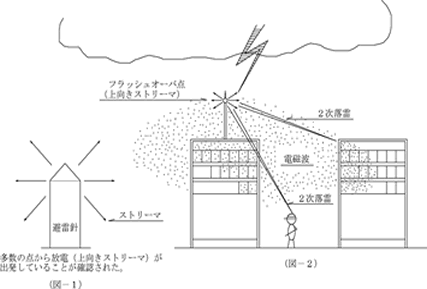 |
|
先端先他側面等に多数の雷撃痕
|
 |
| 同上写真は栃木県日光明智平ロープ−ウェイ頂上中禅寺湖のいろは坂監視カメラ及びNHK放送「おはようお天気カメラ」の上に設置されていた「避雷針」。避雷針を設置した夏から毎年2〜4回らくらい落雷を受けて破壊され映像が送信できなくなってしまい、受雷針及び受雷装置に改修してからは毎年落雷があるにも関わらずこの五年間一度も事故がないとの報告だった。(平成13年8月確認) |